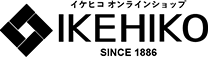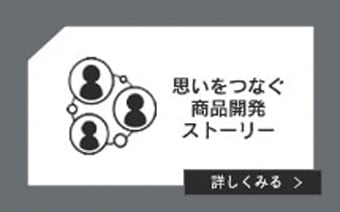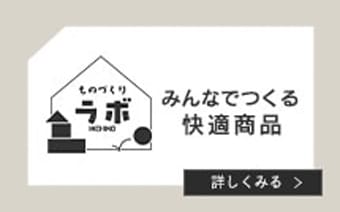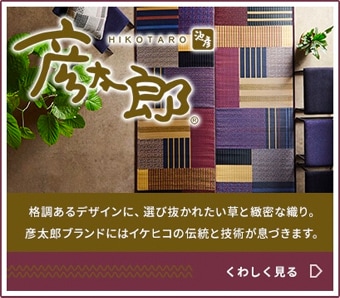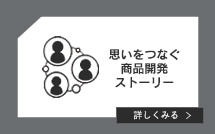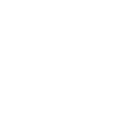寝ござ・い草シーツ
まとめ買いキャンペーン
※買い物カート先で割引が自動的に適用されます。
-
- 国産い草シーツ 寝ござ いやし 日本製
- ¥5,980(税込)〜
-
5.0(1)評価1評価2評価3評価4評価5
-
- 敷きパッド い草シーツ 白水 リルマ シングル 抗菌防臭 消臭 国産い草
- ¥3,990(税込)〜
-
- い草ベビー用お昼寝マット ニーノ 保育園用
- ¥3,990(税込)〜
-
5.0(1)評価1評価2評価3評価4評価5
-
- い草ベビー用シーツ ニーノ
- ¥2,490(税込)〜
-
- こどもおひるねい草ふとん
- ¥7,980(税込)〜
-
5.0(1)評価1評価2評価3評価4評価5
-
- 国産い草 ベビーシーツ&枕セット soi-ne
- ¥6,980(税込)〜
-
- い草シーツ soi-ne 88×180cm 国産 寝ござ
- ¥8,980(税込)〜
-
- 介護 ベッド さらっと敷パッド 88×180cm シングル 防臭 消臭 い草シーツ
- ¥8,250(税込)〜
-
- 寝ござ シングルサイズ ことり 70×180cm い草シーツ
- ¥5,980(税込)〜
-
- 寝ござ ベビーマット ことり 70×120cm
- ¥3,980(税込)〜
- 1
最近チェックした商品 Recently Viewed Products
商品カテゴリー
ラグ・カーペット・マット
すべて
デザイン
カラー
サイズ
機能
置き畳
すべて
ヘリ付き
ヘリなし
い草
PP
軽量
和モダン
リビングにおすすめ
赤ちゃんにおすすめ
形/サイズ
い草ラグ
すべて
国産
円形/楕円形
60×180cm
95×150cm
95×190cm
120×180cm
128×200cm
140×200cm
180×180cm
180×240cm
191×191cm
191×250cm
191×300cm
240×240cm
240×320cm
261×261cm
261×352cm
上敷き
すべて
江戸間
団地間
三六間
本間
六一間
畳の張り替え
すべて
マット
ウィルトンマット
玄関マット
キッチンマット
バスマット
クッション・座布団
すべて
布団寝具
すべて
こたつ
こたつ布団
こたつ布団 機能
こたつ布団 型・サイズ
こたつ布団 柄
カラー
こたつ敷き布団
こたつセット
こたつテーブル
い草・自然素材商品
い草すべて
家具・雑貨
すべて
介護・ヘルスケア用品
すべて
オーダー加工
すべて